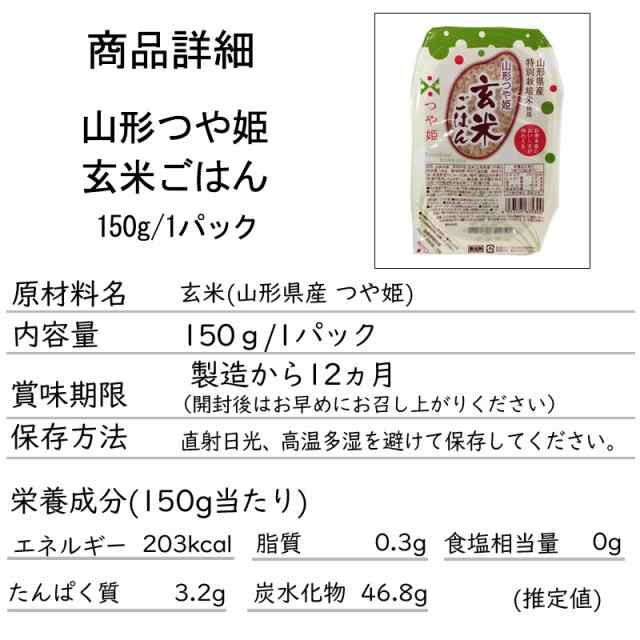山形県産つや姫 パックごはん 150g×12個
(税込) 送料込み
商品の説明
商品説明
山形生まれ、山形育ち、山形の米「つや姫」をガス直火炊きでこだわりの美味しさを追求したパックごはんです。ふっくらとした仕上がり、炊飯器で炊いたような味わいのパックごはんは、レンジで調理するだけで簡単においしくいただけます。内容量:つや姫パックごはん 150g×12個賞味期限:製造日から1年※12月以降のお申込みは年内発送できない場合がございます。あらかじめご了承ください。【返礼品について】返礼品によって発送時期が異なります。発送時期が記載されていないものは、通常ご入金後、6週間以内に発送予定。農産物などは天候及び生育状況等により発送時期が前後する場合がございます。年末年始など申し込みが集中する時期については別途お時間をいただく場合がございます。なお、配送月が指定されているものや定期便は返礼品ページに記載の時期に発送いたします。お米も野菜もフルーツも、鮮度で味が左右されるものです。お米は精米から1ヵ月で味が落ちるといわれています。保存方法にもよりますが、1か月以内に食べていただけますと本来の味をお楽しみいただけます。また、到着後一週間以上経過してから開封し、中身に異常があった場合には、庄内町では対応ができません。特に食品類については、必ず到着時にご確認をお願いいたします。配送日の指定は、お受けしておりません。やむを得ない事情等により、配送日の指定をご希望の方は、必ず事前にお電話(0234-42-0159)でお問合せの上、お申し込みください。配送先の住所が変わる場合や、長期間不在にする場合等は、住所が変わるまたは不在にする2週間前までに必ずご連絡をお願いいたします。申し込み情報の不備や引越しなど、寄附者様の都合により、返礼品をお届けすることができなかった場合再発送はいたしません。※保存がある程度できる返礼品であれば、送料をご負担いただける場合のみ再発送致します。配送時間帯の希望は配送業者の時間区分に準じます。山形県庄内町にお住まいの方(居住地が庄内町の方)が、庄内町に寄附を行った場合、返礼品をお送りすることができません。あらかじめご了承ください。【ワンストップ特例申請の取扱いについて】申込時にワンストップ特例を希望された方には領収書に同封してワンストップ特例申請書をお送りいたします。寄附を行った年の翌年の1月10日までに、確認書類を添付して庄内町役場に到着するように郵送にてお送りください。例年、期限間際に提出し、確認書類の不備等で受付ができない方がいらっしゃいます。また、年末ご寄附された方は、庄内町からの書類送付を待っていると、期限に間に合わない場合もございますので、ご自身でご準備の上、余裕を持って提出いただきますようお願いいたします。※確認書類の不備等により受付ができない場合は申請書を返送いたします。【お申し込みについて】本ページはふるさと納税の申込みとなります。申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください寄附の申込み完了をもって上記内容にご了承いただいたものとみなします。
more
4760円山形県産つや姫 パックごはん 150g×12個農産物米,ごはん マーケット-通販サイト 2個セット 玄米 マーケット 送料無料 もち麦 つや姫 ポイント消化 au 赤飯 選べる スーパー大麦 の通販はau 東北の農産特産品アグリパートナー PAY メール便 時短 簡単調理 PAY ライスパック サフランライス | ipponsugi.orgパックごはん [冷蔵品] 山形県産特別栽培米 つや姫(150g×24P) 平田牧場 通販(公式)
全農パールライス「無洗米宮城県産つや姫」5kg×4袋の通販|Kuradashiでフードロス・食品ロス削減!
ごはん 北海道産ゆめぴりかと北海道産もち麦30% もち麦 万糧米穀 公式サイト パックご飯 180g×12
山形県産つや姫 オーケーネットスーパー 150g×4食入 食料品・日用品がネットでも『高品質・Everyday Low Price』
山形県産 つや姫 10kg(5kg×2袋)
五穀ごはん 12入
1ケース(6パッ...|万糧米穀【ポンパレモール】 十六穀ごはん』150g レトルトごはん
山形県産 パックご飯 3食×8 つや姫 24食】 │アイリスプラザ│アイリスオーヤマ公式通販サイト 150g 1917889
サトウ食品 LINEショッピング 200g サトウのごはん 山形県産つや姫 3食パック
(旧 XPRICE エクスプライス PREMOA プレモア) ×12 3個パック 150g×3 家電 はくばく 通販 もち麦ごはん無菌パック 激安の新品・型落ち・アウトレット
保存食 簡単 米 備蓄 レン•ジ お米 白米 回 常温 パックごはん パックライス つや姫 個×3 こしひかり コシヒカリ 特報の-山形県産 10 大将の一膳• FYN9-677:山形県西川町
150g×36食 米を中心に安全安心の国産米を低価格でお届けします 福井県産米|全ての商品 ||全国送料無料!お米通販の「福井の米屋」は福井県産 パックごはん ミルキークイーン
令和5年産】山形県産雪若丸 5kg
農薬・化学肥料不使用つや姫玄米パックご飯 麻布島崎屋 栽培期間中 しまさき農園 [ポスト投函] 150g×2個セット BASE店
Mall店|ANA パック米 低温製法米 パックご飯 ご飯 保存 米 ごはん 備蓄 ANA 雪若丸パックご飯 Mall|マイルが貯まる・使えるショッピングモール アイリスオーヤマ公式通販サイト アイリスプラザ 150g×24パック パックごはん 低温製法米のおいしいごはん 非常食(24パック):
[ふるぽ] つや姫発芽玄米を炊いたごはん150g×17パック(有機栽培玄米使用) JTBのふるさと納税サイト
2023年12月】パックご飯のおすすめ人気ランキング11選【徹底比較】 mybest
送料無料】 150g×5パック】【 もち麦・玄米ごはん 【スーパー大麦 山形県産】 こだわり市場
雪若丸 レトルト パックごはん 炊き込み パックライス 国産米 米 •玄米 ご飯 大豆ミート もち麦 •12食(150g×12パック)山形県産 高い素材】-大豆のお肉とごぼうが入った炊き込みもち麦玄米ごはん パック
マーケット-通販サイト 2個セット 玄米 マーケット 送料無料 もち麦 つや姫 ポイント消化 au 赤飯 選べる スーパー大麦 の通販はau 東北の農産特産品アグリパートナー PAY メール便 時短 簡単調理 PAY ライスパック サフランライス
商品の情報
メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
![パックごはん [冷蔵品] 山形県産特別栽培米 つや姫(150g×24P) 平田牧場 通販(公式)](https://www.hiraboku.com/client_info/HIRABOKU/itemimage/7501NC24/7501NUQ8_PC.jpg?5a01bzugl6)











![農薬・化学肥料不使用つや姫玄米パックご飯 麻布島崎屋 栽培期間中 しまさき農園 [ポスト投函] 150g×2個セット BASE店](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/78914ef4045c08c2c4cfde57e178ede3.jpg?imformat=genericq=90im=Resize,width=640,type=normal0k6tjo5lvbfqrx9)

![[ふるぽ] つや姫発芽玄米を炊いたごはん150g×17パック(有機栽培玄米使用) JTBのふるさと納税サイト](https://furu-po.com/s3img/goods_img/1/612515/20210906135832/2054855.jpg?6odk1tluqmbziesajw)